
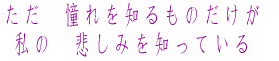
 |
僕の本棚には 学生時代に作った ガリ版刷りの 同人誌 20冊ほどと 当時のビラ数枚が 棄てられずに 残してあります。 あの時代に 活字になれなかった 散文たちを ここで やっと 活字にして あげることができました。 さとちゃん |
白い街で 佐藤 さと
生きるといことは哀しいことだと思う。
名古屋のことを白い街と唄うのは
センチメンタルシティロマンスだったっけ。
江口 晶だったっけ。
歩道に敷き詰められて
眩く反射するコンクリートの色は
確かに白かった。
この道をまっすぐ行くと
湿った匂いのする
古本屋がある。
「ちょっと古本屋に行くけれど、
ケンはどこかへ行くのかい。?
一緒に行ってみないかい。?」
と、今朝友人に
電話をかけたが
ケンは
「えへへ、ドライブ。直ちゃんと。琵琶湖まで・・・」
デイトらしい。
「仲良く、やってこいや。気をつけてな。」
少し、自分が惨めに思えた。

ころころと街路樹から
落ちた
春の枯葉
一枚。
白い歩道で
踊りだす。
歩道の地面に映る僕の影が
薄かった。
肩が狭くて、下がっている
僕の華奢な姿を
映していた。
何時もこうなんだから・・・
と
僕は諦めようとする。
忘れようと努力する。
ひとには
思い出してよい記憶と
忘れてしまった方がよい記憶があるものだ。
今朝からの僕のなかには
その忘れてしまった方がよい
思い出ばかりが
走馬灯のように
ぐるぐると回っていた。
哀しいセロハンの色が
次々と僕の網膜に映しだされていった。
忘れてしまいたい、
暗く、悲しい思い出など。・・・
しかし
悲しく辛い思い出は
僕のこころに まとわりついていた。
こういった日には
諦めるという行為さえ諦めてしまい
自棄的に酒を呑んだりしていたが
今朝は
家を出たかった。
目的もなく
街を
歩きたかった。
今の僕には
ただ 歩くことが
目的なのかも知れない。
ただ
独りで歩くのは
辛かった。

見慣れたいつもの古本屋を
通り過ぎて暫くすると
何時の間にか
鶴舞公園に辿りついていた。
新緑の若葉の息吹は
生々しい匂いを発散させていた。
木陰のベンチに腰をかけ
僕は
今日十三本目の
ハイライトを吸い始めた。
誰もいない。
小鳥もいない。
そんな
生き物のいない所で
僕の存在を知っているのが
僕だけであるように
僕の淋しさを
知っているのは
僕だけかも
知れなかった。
小学校の頃
ひとりで木登りをして遊んでいて
誤って木から滑り落ち、足首に怪我を
したことがある。
赤い血が
さらさらと
運動靴に流れ込み
気持ちが悪かった。
懸命に足を引き摺りながら
家に戻った。
母から預けられた鍵で
扉を開け
夢中で
救急箱を捜した。
捜している間に血が
点々と
畳に落ちた。
やっと
救急箱を見つけて
誰もいない部屋の隅っこで
血をガーゼで拭い
赤チンを
脱脂綿に含ませて
塗り始めたら
急に
今まで出なかった
泪が
大粒で
流れてきた。
痛みも急に増してきた。
そんな
思い出があった。
何よりも
心細かったのであろう。

誰にも言えない思い出がある。
言ってもどうしようもない
くだらない思い出がある。
そんな僕の思い出を
聞いてくれる友人は
恋人は
今の僕には いなかった。
ひとりだけ
僕の思い出を
きいてくれた人がいた。
去年の夏
バイト先で知り合った女の子だ。
「淋しい時は・・・・
お酒、 飲むと・・・・
いいわね。」
明るく無邪気に話していた彼女が
ふいに そっぽを向いて
一言、言った。
彼女は貧血症のため
一週間で
バイトを辞めてしまった。
それから
そのあとは 会ったことがない。
今 僕は
彼女がお酒を
飲まないように生きていれば・・・
と、祈っている。
彼女には
哀しい思い出を作って欲しくないのだ。
哀病は僕だけの
病気でいい。
淋しく哀しい思い出は
僕の中に
毎年蓄積していた。
すっかり
慢性化した哀病は
今までの
僕の
生
そのものかも知れない。
若いアベックがこちらへ
歩いてきた。
彼女の方は
腕をくみながら
少し はにかんでいる。
ー優しそうなひとだな。ー
バイトで会った女の子に少し似ていた。
僕は、公園のベンチから
腰を浮かした。
古本屋へ戻ろうと思った。

歩いて行く間に
僕の意識は 夢と現実の世界が
交錯していた。
何時か夢で見たような
気がする街を歩いて行くと
思い出のひとに出逢えた。
「さとくん、元気?・・・」
「ああ、おおむね。」
「クスクス、変わらないのね。ずっと。」
「変わらないところも、有るかも知れない。」
「痩せたね。少し・・・。」
「煙草、吸うからな、俺。一日二十本以上も・・・。」
「元気でね。」
「明子さんも、元気でね。」
「さよなら。」
「さよなら。」
僕の恋はいつも片思いであった。
朗らかに笑う、健康的な明子さんに
僕は中学校三年生の時、
密かに憧れていた。
彼女が
彼女の友人たちと雑談していた時
妙に、彼女にそぐわない
大人びた言葉を
聞いたことがあった。
「明子さんは、いつも幸福そうね。」
「でも、私は孤独よ。・・・本当は・・・。」
僕は彼女と二人きりで
話したことは一度もなかったし、
もちろん、どこかへ
遊びに行ったこともなかった。
けれども
彼女は僕に時々
思いやりを与えてくれた。
「食いしんぼの さと君。
これ、食べて。
家庭科の授業で
私が作ったサラダなんだから・・・。」
と、給食の時
半分僕の皿の上にのせてくれた。
「えっ、本当にいいんかい。僕に・・・。」
顔が赤くなるのが自分でもわかった。
正月には
おもいがけない
年賀状が彼女から届いた。
彼女は知っていたのだろうか?
僕が密かに彼女に憧れていたことを・・・
明子さんは
高校一年生で中退して
すぐ、結婚したと風の噂で聞いていた。
中学校以来
会ったことのなかった彼女が
乳色の霧の中からすうっと現れ
そして
消えてしまった。
これは夢なのだ・・・

薄暮の混沌とした街の路地を
抜けかけた時
一人の少年が
うずくまっているのを
見つけた。
「あ、さと君。
へぇ、もう、大学生になったの。」
振り向いた
あどけない少年は
小学校六年の時
病気で死んでしまった友達の
安ちゃんだった。
「安ちゃん。
安ちゃんじゃないか。
けれど
君は死んじゃったたんだろう?」
「死んだけれども、
まだ、僕はこの世にいるよ。
こうして、ここで
豆電球のなかを覗いていると
同級生が
時々
この路地を通っていくんだ。
でも、ネクタイを
締めなおしたり、
週刊誌を読みながら皆、通り過ぎてしまい
僕に気付かず
歩いていってしまうんだ。
みんな、変わってしまったね。
あのガキ大将だった奥村なんか
すごい髭を生やしていたんだぜ。・・・
真面目に働いているみたいだよ。
汗の匂いが
プンプンしたんだ。」
「へぇー、あの奥村が・・・。」
「さと君、頼みがあるんだ。
単三電池を一本買ってきてくれないか?
電球を点けている電池が
もうすぐ切れそうなんだ。
電池が切れたら
電球のなかに住んでいる小人が
死んでしまうから・・・。」
「僕の電気カミソリのでよかったら
二本あるから、
これ、あげるよ。」
「ありがとう。
さと君には
いろんなものをもらったね。
登山ナイフとか、ビー玉だとか・・・、昔。
ありがとうな。
皆、うちが貧乏だったから、
馬鹿にして遊んでくれなかったのに・・・」
「いいんだ。安ちゃん。
僕もあの頃、嘘つきで仲間外れだったし・・・
誰か一緒にビー玉遊びとかキャンプ遊びを
したかったし・・・・
安ちゃんは、
僕にカブト虫やクワガタ虫を
くれたじゃないか。」
「そうだったっけ。
あっ、さと君。
さよなら。
電球のなかの小人が
元気なって
僕にガラスのなかへ
遊びに来いって言っているんだ。
じゃ、バイバイ」
「ちょっと待ってくれ。
僕もその世界に入りたいよ。」
「これだけは無理だよ。
さと君はまだ生きているもの。
これからも
思い出を増やして
いかなくっちゃいけないんだもの。
バイバイ。」
安ちゃんは
電球の中に吸い込まれていった。
「安ちゃん。僕も
死んじゃうかもしれないよ。もうすぐ。・・・」
しかし、その声は
届かなかった。
僕はまた独り取り残された。
夢から覚めると
黄昏の街が浮かび、水銀灯が白く輝いていた。
南東の風は
確かに春の風だった。
ひどく心細い気持ちが
僕の心のなかにある
と思った。
〔二十歳〕
|
次頁へ |

